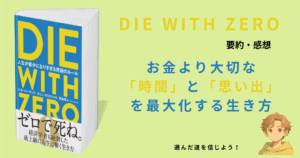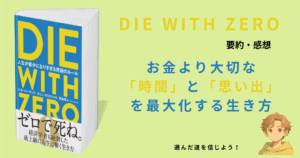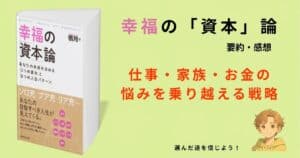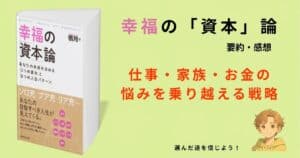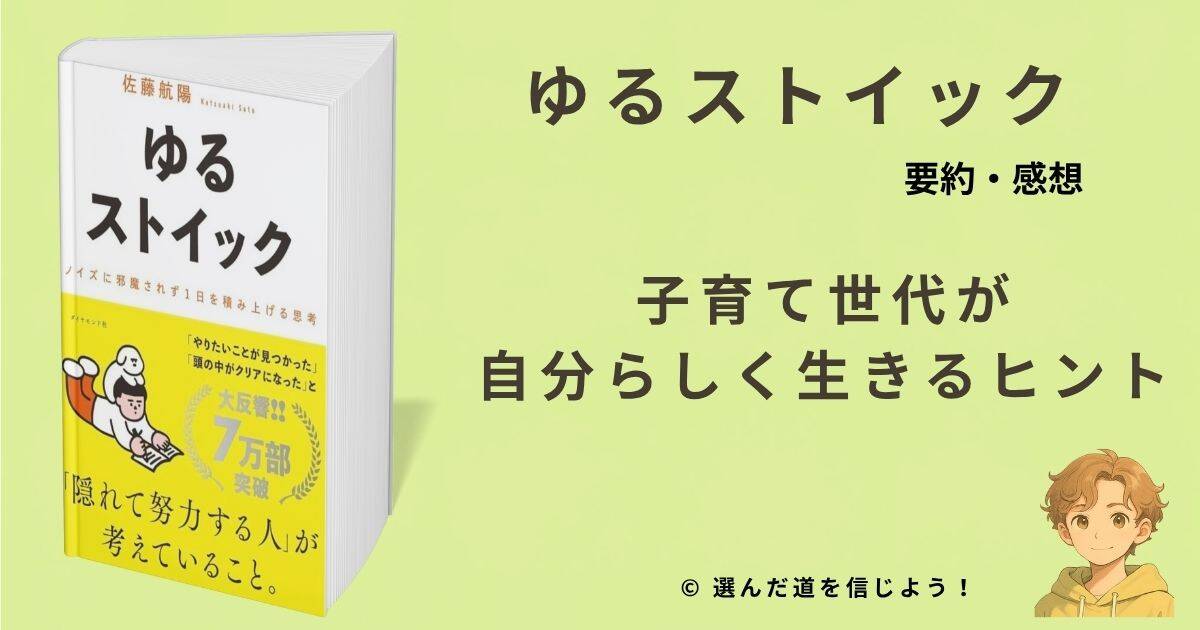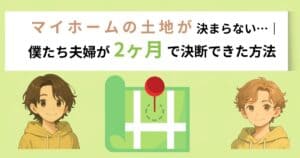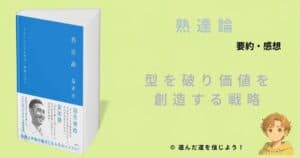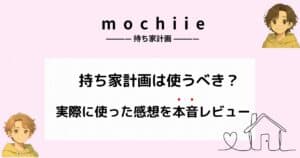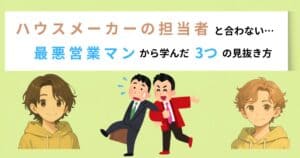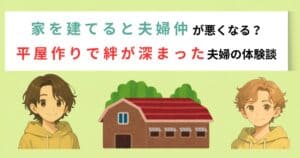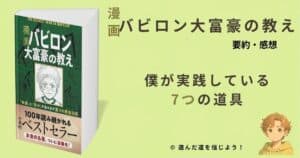ぽんちゃん
ぽんちゃん「もしかして、自分って頑張りすぎてないのかな…?」 子育て、仕事、副業…やりたいことはたくさんあるのに、思うように進まない…。
SNSで他人の成果を見ては落ち込んだり、「もっと頑張らないといけない…」と自分を責めてしまう。
そんな毎日に、ふと「ゆるストイック」という言葉が心に刺さりました。
とはいえ、僕は子育てと仕事に追われる中で「自分らしく、でも無理せず成長したい」とずっと思っていました。
そんな時に出会ったのが、今回ご紹介する『ゆるストイック』です。



この記事では、僕自身の体験や悩みを交えながら、「ゆるストイック」な生き方が子育て世代にどんなヒントをくれるのか、わかりやすく伝えしていきます。
この記事を書いた人【まるちゃん】


- 30代会社員
- FP3級取得
- 副業は2年間継続中
- Kindle出版でベストセラーを獲得
- 平屋のマイホームを建築中
- 僕のプロフィールはこちら
本書のポイント


最初に僕が感じた3つのポイントを紹介します。
- 「ゆるストイック」は、完璧主義を手放し”自分のペース”で続けることの大切さを教えてくれる
- 情報過多や他人との比較から距離を置き、集中力と行動力を取り戻すヒントがたくさんある
- 小さな積み重ねと、無理のない習慣化が、子育て世代の自己成長にぴったり!



これから本を詳しく紹介していきます!
「ゆるストイック」ってどんな本?
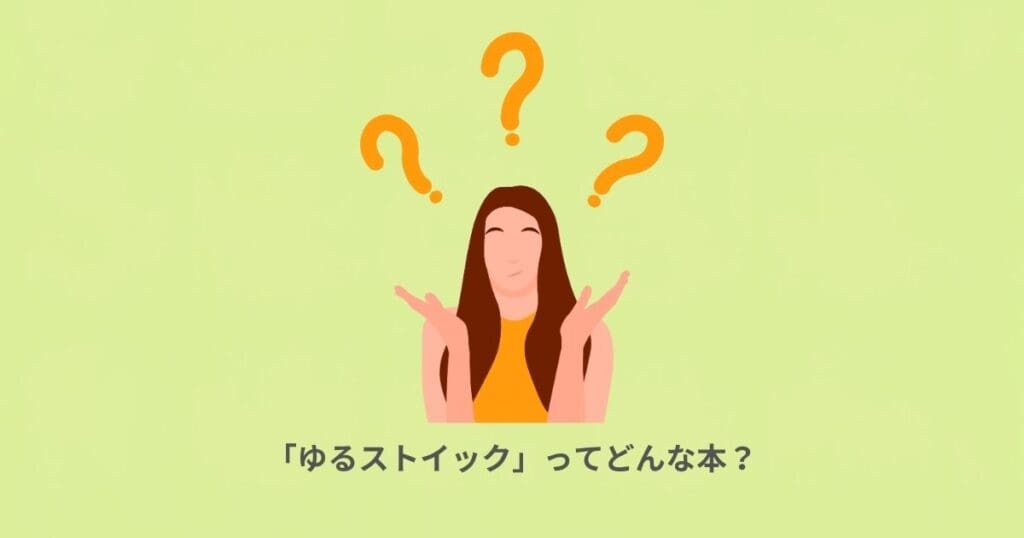
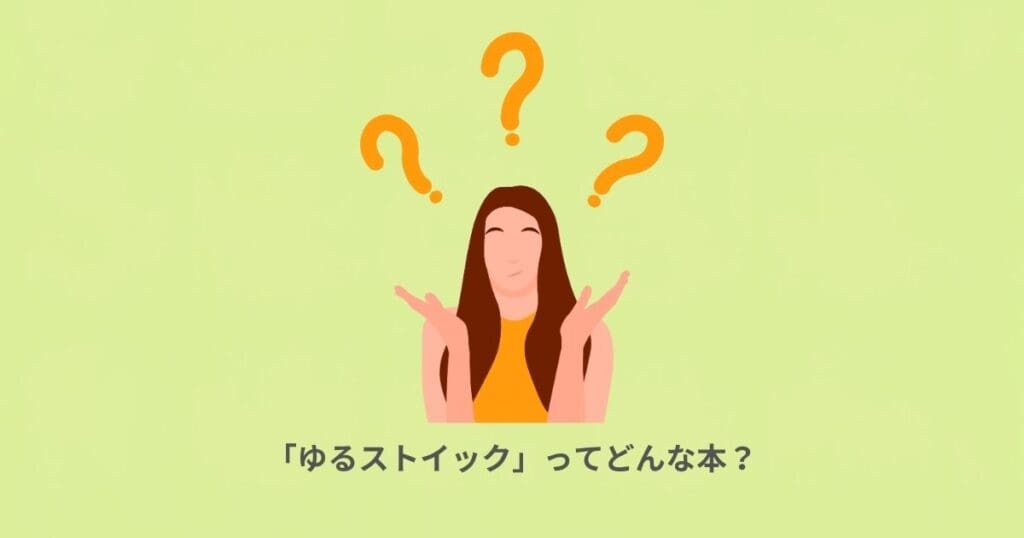
「ゆるストイック」とは、一言で言うと「無理せず、自分のペースで続けるストイックさ」。
著者の佐藤航陽さんは、華々しい経歴を持つ一方で、現代人が抱える”頑張りすぎ”の問題に寄り添い、「ゆるさ」と「継続」のバランスを提案してくれています。
「ストイック=自分を追い込むもの」と思いがちですが、「ゆるストイック」は”自分を大切にしながら、少しずつ前進する”新しい生き方なんです。
| 書名 | ゆるストイック-無理せず自分を成長させる「続ける」技術- |
|---|---|
| 著者 | 佐藤航陽 |
| 出版社 | ダイヤモンド社 |
| 発売日 | 2025年2月18日 |
| ページ数 | 288ページ |



変化の激しい現代の社会を乗りこなすためのバランスの取れた新しいアプローチになりそうですね!
「ゆるストイック」を読んで感じたことや気づき
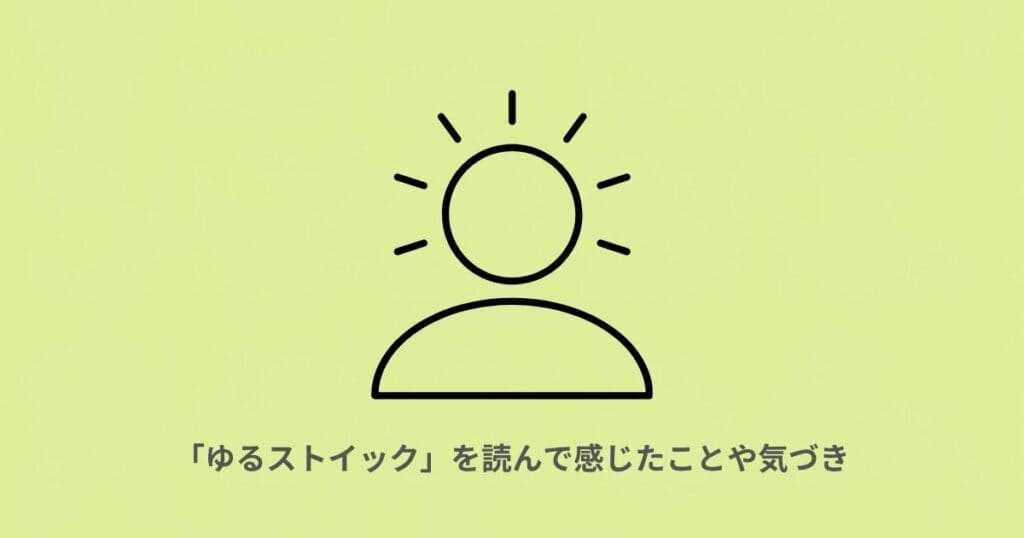
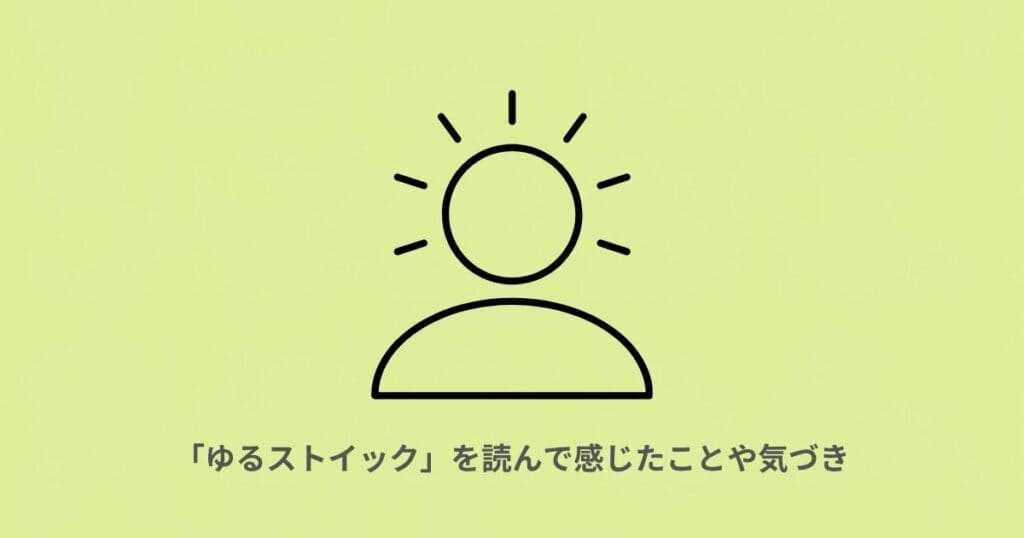
「ゆるストイック」を読んで、まず感じたのは「自分のペースで無理なく続けていいんだ」という安心感でした。
これまで僕は、何か新しいことを始めるときに「完璧にやらなきゃ」と思い込んで、なかなか一歩が踏み出せなかったり、途中で疲れてしまうことが多かったんです。
でも、この本を読んで「小さく始めて、少しずつ続けることが大切」というメッセージにとても救われました。
また、SNSやネットの情報に振り回されて、他人と自分を比べて落ち込むこともよくありましたが、「情報のノイズを減らして、自分の集中できる環境を作る」という考え方も印象的でした。
「頑張りすぎなくていい」「自分を追い込まなくていい」「できる範囲で続けていけば、それが一番の近道」という、やさしいエールをもらえた気がします。



自分のペースで、できることから始めることの重要性を改めて学び直すことができました!
「ゆるストイック」な生き方の3つのコツ
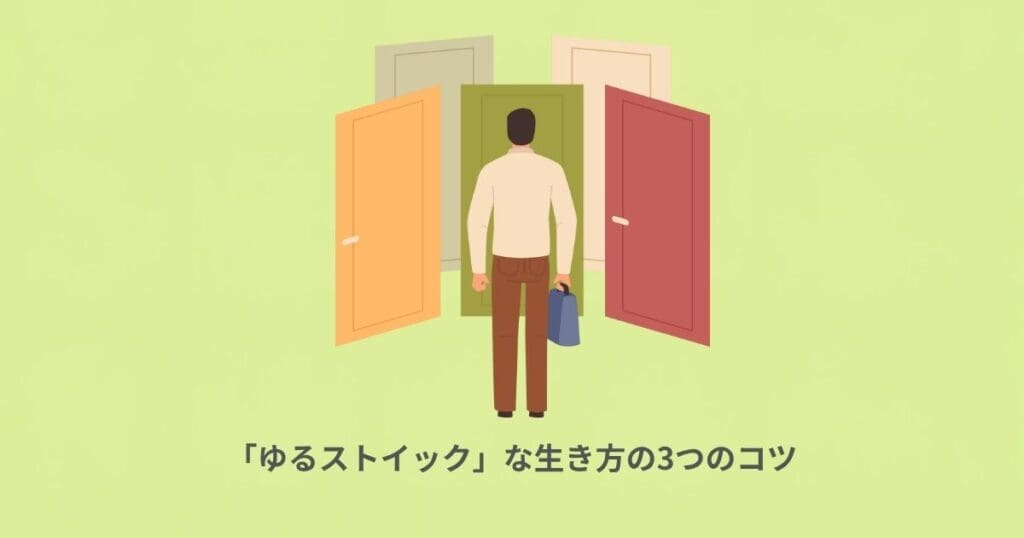
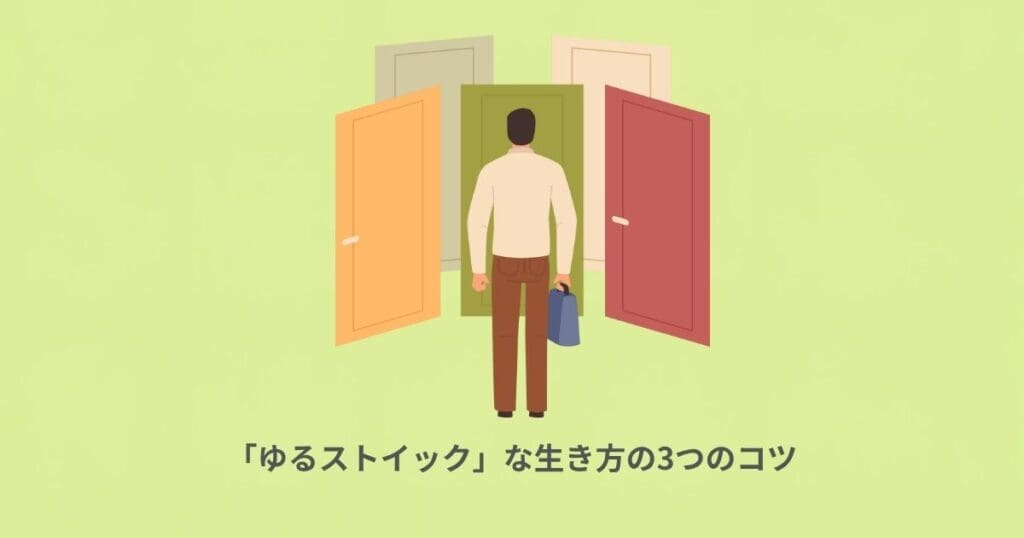
「ゆるストイック」な生き方を実践するためには、いくつかのポイントがあります。
本書を読んで特に印象に残ったのは、以下の3つ。
これらのコツを意識することで、子育てや仕事に追われる毎日でも、自分らしいペースで成長し続けることができると感じました。



それぞれ3つのコツについて詳しくご紹介します。
1. 情報のノイズを遮断し、集中力を取り戻す
現代はSNSやネットの情報があふれ、つい他人と自分を比べてしまいがちですよね。
僕も、SNSで他人の副業成功談を見るたびに焦りや落ち込みを感じることがよくありました…。
「ゆるストイック」では、SNSの通知をオフにしたり、不要なアプリを削除することで、意識的にノイズを減らすことをすすめています。
実際に、僕も約5ヶ月間SNSを見る時間を減らしたことで、目の前のことに集中できる時間が増えました。



LINE以外の通知をオフにしてみたら、心がものすごくラクになったよ!
2. 完璧主義を手放し、「小さく始める」
副業や新しい挑戦を始めるとき、「完璧にやらなきゃ」と思うと、なかなか一歩が踏み出せませんよね。
僕も新しいことを始めたとき、最初から完璧を目指して手が止まってしまった経験が何度もあります…。
「ゆるストイック」では、「できる範囲で、まずは小さく始める」ことを大切にしている。
1日5分でも、30分でも、続けることが大きな力になると気づかされました。



もし「完璧じゃなくてもいいんだ」と思える暮らし方に興味がある方は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。
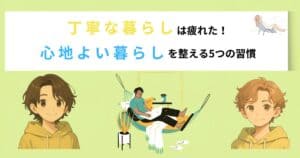
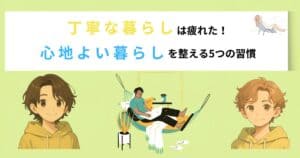
3. スキマ時間と外部サービスを活用して、無理なく習慣化
子育てや仕事で忙しいと、まとまった時間を取るのは難しいもの。
ゆるストイックでは、既存のプラットフォームや外部リソースを「タダ乗り=自身の時間とエネルギーを節約する」活用することが推奨されていました。
僕は、スマホとパソコンで作業を分担したり、UdemyやAudibleなどのサービスを使って、スキマ時間に自己研鑽に励んでいます。
また、ロボット掃除機やドラム式洗濯機などの家電も活用し、家事の負担を減らすことで、自分や家族の時間を生むだす第一歩!



毎日のちょっとした工夫で、無理なく習慣を変えたい方には、こちらの記事もおすすめですよ。
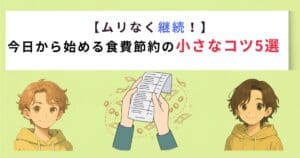
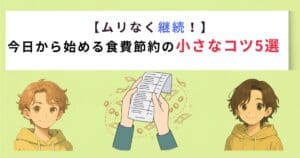
こんな人におすすめ
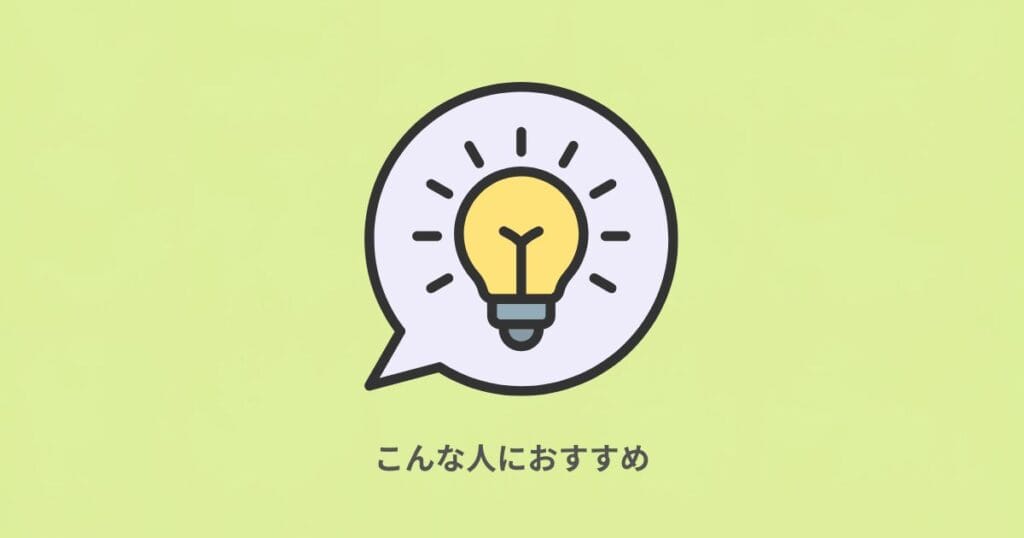
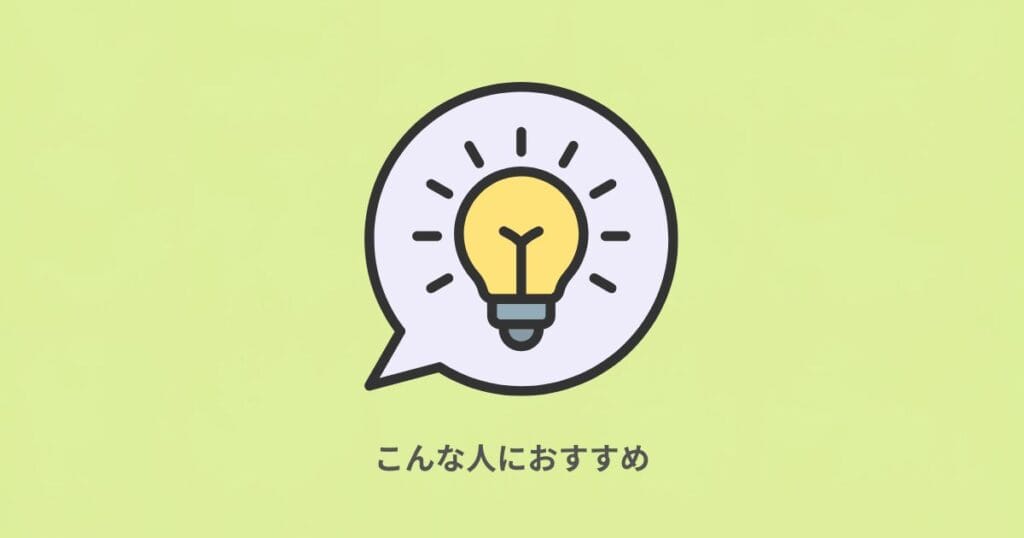
「ゆるストイック」は、これから紹介する悩みを抱えている人にこそ手に取ってほしい一冊です。
- SNSでの情報過多に疲れ、本当に大切なことに集中したいと思っている
- 完璧主義が邪魔をして、なかなか新しいことに挑戦できない、あるいは行動に移せないでいる
- 「時間がない」を言い訳に、副業やスキルアップを始められずに悶々としている
- 目標達成に向けてストイックになりすぎると疲弊してしまうため、「無理なく継続する方法」を探している
- 漠然とした焦りや不安を感じており、もっと前向きな気持ちで日々の生活を送りたい



特に継続が苦手で、無理なく自己成長の習慣を身につけたいと考えている人には絶対オススメです。
よくある質問と回答


ここでは、「ゆるストイック」を読みたいけれど迷っている方からの疑問に僕なりにお答えします。
子育てや仕事で本当に時間がない私でも、この「ゆるストイック」を実践できますか?
この本はまさに、まとまった時間が取れない現代人のために書かれていると言っても過言ではありません。完璧を目指さず「自分のできる範囲で小さく始める」ことの重要性を説いており、1日5分といったスキマ時間でも効果的に学びや行動を積み重ねるヒントが得られます。僕自身、子育ての合間にスマホやPCで作業を分担するなどして実践し、着実に成果を感じていますので、多忙なあなたにも無理なく取り入れていただけるはずです。
「ゆるく」という言葉の響きに惹かれますが、結局何も成果が出せずに終わるのではないかと不安です。本当に「怠け」に繋がらずに続けられますか?
「ゆるい」と聞くと、つい「怠ける」ことと結びつけてしまいがちですよね。しかし、本書でいう「ゆるさ」とは、決して努力を放棄することではなく、完璧主義を手放し、無理なく継続するための知恵です。むしろ、完璧を目指すあまり行動が止まってしまうのを防ぎ、小さな成功を積み重ねることで、結果的に大きな力を生み出すことを目的としています。
SNSなどで他人の華やかな成果を目にして落ち込むことが多いのですが、この本はそうした「ノイズ」から解放される手助けをしてくれますか?
まさにその悩みにこの本は深く切り込んでいます。SNSの通知オフ、不要なアプリの削除、意識的なSNSからの距離の取り方など、具体的な「ノイズの遮断」方法が示されており、実践することで他人との比較による心理的な負担を軽減できます。情報過多の現代において、本当に集中すべきことに力を注ぎ、心の平穏を保つための強力な指針となるでしょう。
過去に自己啓発書を読んでも行動に移せなかった経験があります。この本は、本当に私の行動を変えるきっかけになりますか?
過去の「積ん読」経験は、僕にもありました。しかし、この本が他の自己啓発書と一線を画すのは、「ゆるく始める」という実践的なアプローチを重視している点です。壮大な目標を立てるのではなく、1日5分でもできることから始め、それを習慣化する。この「小さな積み重ね」の重要性を深く理解することで、無理なく行動が継続できるようになります。単なる精神論ではなく、具体的な行動へのヒントが詰まっているため、今度こそ行動を変えたいと願う方には強くお勧めできます。
「ストイック」という言葉に抵抗があるのですが、それでもこの本は私に合いますか?
大丈夫です。むしろ「ストイック」という言葉に疲弊感を感じる方にこそ、この本は読んでいただきたいです。本書のタイトルにある「ゆるストイック」は、決して自分を追い込むことを推奨しているわけではありません。完璧主義を手放し、無理なく、着実に、そして継続的に物事を進めるための新しい「ストイック」の形を提案しています。読めばきっと、「ストイック」に対するあなたのイメージが変わり、自分に合ったペースで頑張ることの大切さに気づくはずです。
まとめ:あなたも「ゆるストイック」な一歩を


「ゆるストイック」は、頑張りすぎて疲れてしまった子育て世代にこそ、ぴったりの生き方です。
完璧を目指さず、情報のノイズを減らし、自分のペースで小さく始める。
そんな”ゆるさ”が、実は一番の近道かもしれません。
あなたも今日から、「ゆるストイック」な一歩を踏み出してみましょう。



無理しないで、一つずつできることから始めてみようね!